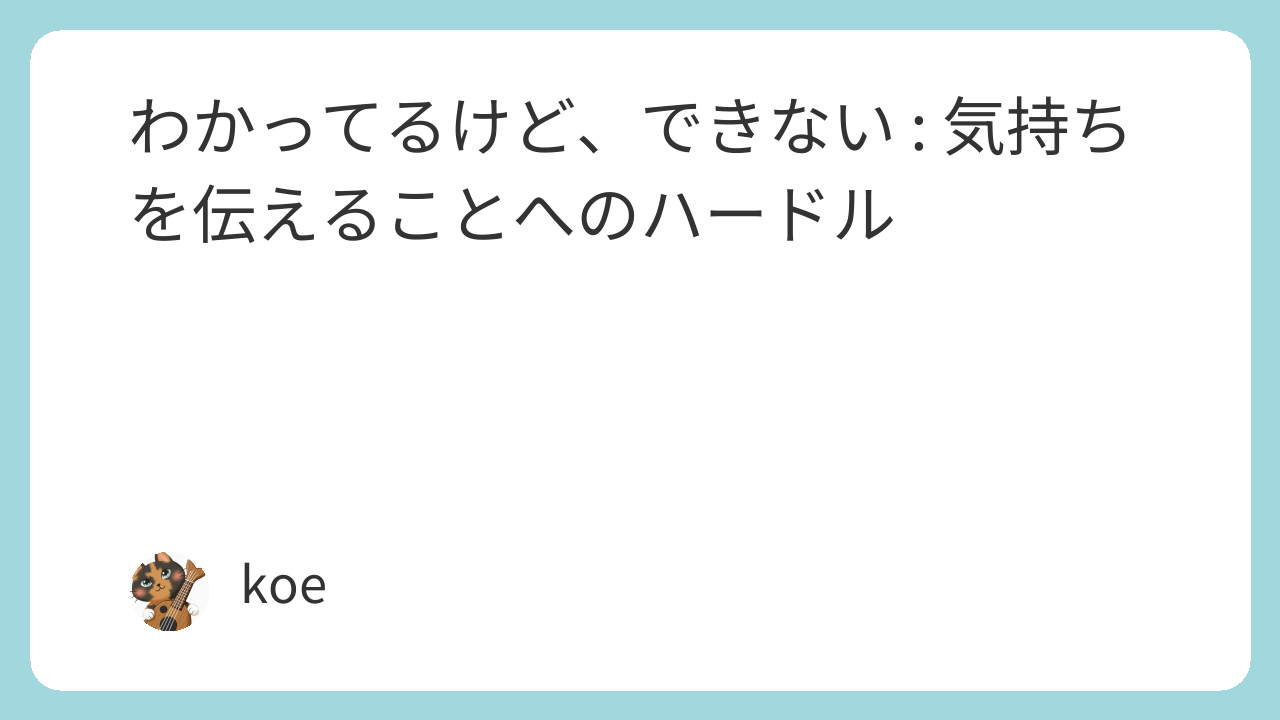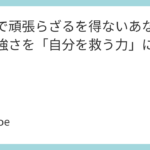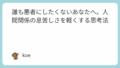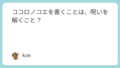はじめに
AIの力を借りてブログを書こうと思ったのは、自分で書くと生々しい感情が出てしまい重くなると思ったからです。とは言え、試行錯誤しながら仕上げるので頭は使います。次第に思考も整理され、研ぎ澄まされてゆくようです。
最近は、他者が私をコントロールしようとしている感覚に敏感になってきてしまいました。
けれど「彼らに悪気はない」という立場はできれば手放さない方が生き易いような気はするので、そこはいじらず自分が楽になるには…
自分の気持ちを言葉にして伝える
やはり、これに尽きるのではないか?と思いました。
STEP1: 気持ちを伝えることへのハードルに気づく
どうすれば、気持ちを楽に伝えられるようになるだろうか?を考える前に気づいたことがあります。
今の私はそれに苦手意識というか、抵抗感があるのです。なぜでしょう?
若いころはもっと愚直に自分の気持ちをぶつけていたような気がするんです。でもある時からそれがうまく行かなくなったのです。たぶん。
考えられる理由をあげてみます。
1.「伝えても無駄」という経験の積み重ね
原因:私が前向きな意欲や気持ちを言葉にしても、相手はそれに理屈を並べたり、自分の都合を押し付けたりして、私の気持ちが受け止められないことが繰り返された。
結果: 「どうせ言っても変わらない」「言ったところで、また水をさされる」という諦めが生まれ、言葉を尽くすエネルギーを消耗することから逃れたいという気持ちになる。
2.自己肯定感の低下と自己嫌悪
原因: 気持ちを言葉で伝えようと努力しても伝わらず、最終的に「キレてヤケクソになってしまう」という行動に至ることがある。
結果: その後の自己嫌悪や無力感から、「こんな自分はダメだ」と自己肯定感が下がり、気持ちを伝えること自体が「自己肯定感を下げる行為」として無意識に避けられるようになる。
3.「どうせ自分はこんな人間」という防衛機制
原因: 理想の自分になろうと努力しては失敗し、そのたびに傷つく経験を繰り返す。
結果: 傷つくことを避けるために、「どうせ自分はこんな人間だから」と期待値を下げ、自分自身に諦めのレッテルを貼ることで、一時的な安心を得ようとする。
4.空気を読まず自己主張すること=良くないという刷り込み
原因: 集団の調和を重んじる文化の中で育ち、「空気を読むこと」が美徳とされる刷り込みを無意識に受けている。これにより、自分の意見を率直に伝えることは「わがまま」や「波風を立てる行為」だと感じてしまう。
結果: 相手を不快にさせたり、場の雰囲気を壊したりすることへの罪悪感が生まれる。その結果、自分の気持ちを心の中に押し込めることに慣れてしまい、いざ伝えようとすると、どう表現していいかわからなくなったり、自己主張自体を避けるようになる。
5.関係性の「ホメオスタシス(恒常性維持機能)」
原因: 私が前向きに変わろうとすると、周囲(子供、パートナー、親、知人・友人)が無意識にその変化に抵抗し、「元の状態」に戻そうとする。
結果: 前向きな意欲を出した途端に水をさされるような出来事が起こり、「私の意欲は受け入れられない」「お前はずっと出来損ないのままでいろ」という圧力のように感じてしまう。この感覚が、気持ちを伝えること自体への恐怖心や、無力感につながる。

いや、多くない?!
ハードル多くない?!
特に5番目とか、いい加減にしてって感じじゃない?!
おっと、思わず素が出てしまいました。
これにはきっと人それぞれ色んな理由があると思います。
思いを巡らすだけでも小さな変化があるかもしれないので、よかったら考えてみてくださいね!
STEP2:無理なく自分の気持ちを伝えていくには?
それでは、やっと本題です。
ここまでの流れを共有しているAIに、「次のSTEP2として、どうしたら無理なく自分の気持ちを伝えていけるか提案してください」と指示を出したところ
それが出来たら今頃苦労してないです
1. 「伝える」ことの定義を変える
相手に理解させるのではなく、ただ「放つ」と捉えましょう。「私は〜と感じる」と、自分の気持ちを主語にするI(アイ)メッセージを意識することで、相手の反応を気にせず表現できます。
2. 「伝える」場所と方法を限定する
いきなり対面ではなく、メモやLINEで気持ちを伝える練習を。言葉ではなく、自分の行動で「私の時間が必要」というサインを送る方法も有効です。
3. 伝える「相手」と「内容」を限定する
最初は、愚痴や不満ではなく、ポジティブな感想や感謝の気持ちから伝えましょう。一番話しやすい相手を選び、小さな成功体験を積み重ねていくことが大切です。
知識ではわかっていても出来ないという拒否感があるので、「もっとスモールステップで」とお願いして出てきたのがこちら。
それはまさに今やっていることでは?
1. 感情をただ「認識」する
誰にも何も伝えなくていいので、心の中で呟いてみてください。 「ああ、今、私は嫌だと感じた」 「ああ、今、やる気を削がれたな」
この一瞬の「認識」だけでも、あなたは感情の渦の中に飲み込まれることなく、自分を客観的に見つめることができます。これは、感情に振り回されず、あなたの心の主導権を少しずつ取り戻すための練習になります。
2. 感情を「メモ」に書き出す
電話で嫌な気持ちになった時、帰宅後にメモ帳やスマホのメモ機能に、その時の感情を一行でもいいので書き残してみましょう。 「○月○日、犬の散歩で嫌な気持ちになった」 「なぜかイライラする。疲れた」 これは誰かに見せるためのものではありません。あなたの感情を、あなたの手で記録するだけの行為です。
3. 物理的に「距離をとる」
これは、言葉を使わない最も簡単な自己防衛です。 相手の行動にコントロールされそうになったり、嫌な気持ちが湧いてきたら、その場からそっと離れてみましょう。 「ちょっとお茶入れてくるね」 「トイレに行ってくる」 など、口実は何でも構いません。自分の心を守るために、物理的なスペースを確保することが、一番の解決策になることもあります。
これらのステップは、どれも「相手に気持ちを伝える」というゴールは設定していません。まずは、あなた自身の感情を、あなた自身が優しく受け止めることから始めてみませんか。
始めてる、始めてるからこんなブログ書いてる。
どうしよう、今日の記事上手く着地できないかもしれない。
でももしかしたら、誰かの役に立つかもしれないので残しておきたいと思います。
STEP1.5 : 欲しいのは理想と現実をつなぐ何か
頭の中では「嫌な気持ちを認識して、物理的に距離を取る」という解決策が分かっている。 でも、その知識と行動の間にある、どうしようもない感情の溝。
その溝を飛び越えるのではなく、少しずつ埋めていくための、中間地点の小さな一歩。
中間地点への小さな一歩
1. 言葉を「事実の報告」として使う
相手とのやり取りで、嫌な気持ちが湧きそうな時、感情を伝えるのではなく、ただ「事実を淡々と報告する」ことに集中してみませんか。
これは「私の気持ちはこうだ」と伝えるのではなく、「私はこうします」という行動の予告です。これにより、あなたの行動の主導権を握ることができます。
2. ポジティブな「断り方」をストックする
「嫌だ」と伝えるのが難しい時、代わりに使える短い言葉をいくつか持っておきましょう。
- 「ありがとう、でも大丈夫」
- 「わかった。ちょっと待ってね」
- 「それは、あとで考えるね」
これらは、相手の言葉を一度受け止めつつも、あなたの選択肢を確保する言葉です。相手の言葉に即座に反応せず、考える時間を持つことで、感情的に巻き込まれるのを防ぐことができます。
これらのステップは、あなたに「気持ちを伝える」という重荷を課すものではありません。あなたが感じる「コントロールされそうになる感覚」から、自分を守るための、より具体的で、小さな防御策です。
あまり納得はしていないけれど、やってみる価値はありそうだと思ったので、これを今日の締めとしたいと思います。
「いや、自分はこうする」
そう思ったあなた、それもきっと一つの正解です!