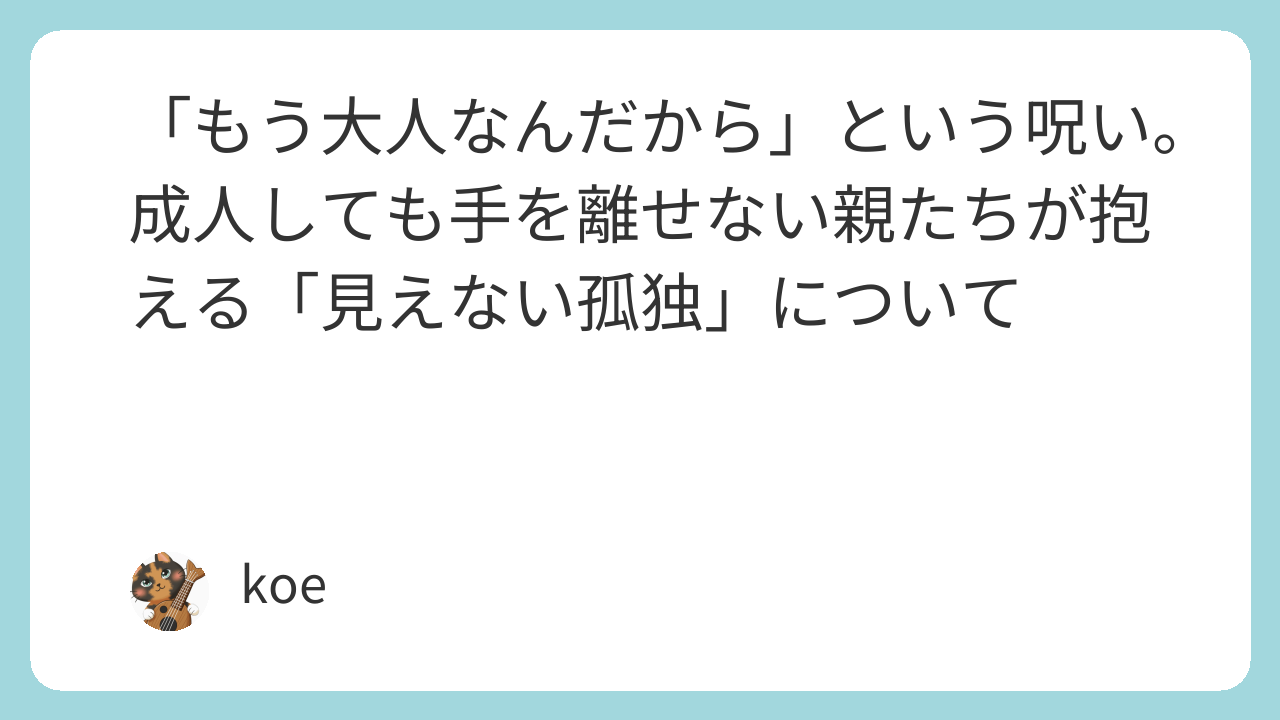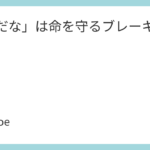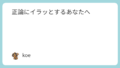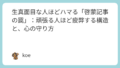子育ての「表」と「影」
子育てという言葉から、どんな光景を思い浮かべますか。 夜泣きに奮闘する夜、公園で砂まみれになる休日。SNSには、そんな大変だけど愛おしいエピソードが溢れています。誰もが頑張ってるねと声をかけやすい、光の当たる表の子育てです。
しかし、子供が18歳、20歳と年齢を重ねるにつれて、その物語は急速に姿を消していきます。 もう大人なんだから。手がかからなくなって楽になったでしょう。 世間は、あたかも全員に一律のゴールテープが用意されているかのように語ります。
けれど今、この社会には、そのゴールが見えずに、暗闇の中で走り続けている親たちがいます。
スポットライトが消えた後の孤独
子供が大きくなり、社会との接点が増えてからの方が、苦労はより複雑で、他人には言えないものへと変質していきます。
特に発達にゆっくりなペースを持っていたり、少し凸凹があったりするお子さんを持つ親にとって、18歳や20歳という数字は、単なる通過点に過ぎません。周りの標準的な時計が「自立」を告げる中で、止まってしまったかのような我が子の時計を、ただ一人で見守り続ける。その孤独は、何歳になっても消えることはありません。
過保護ではなく、必要な伴走
もし今、あなたがいつまで親を続ければいいのだろうという孤独を感じているなら、伝えたいことがあります。
あなたは過保護な親ではありません。社会の標準的な時計よりも、少しだけゆっくり進むお子さんの時計に合わせて、必死にペースメーカーを務めているだけなのです。
18歳で巣立つ鳥もいれば、地面を長く助走してから飛び立つ鳥もいる。 ゴールはカレンダーの日付で決まるのではなく、子供自身が自分のペースで歩き出せたその瞬間に、初めて静かに訪れるもの。周りの正論と比べて焦る必要はありません。
当事者として思う、伴走者の大切さ
私自身、かつてドロップアウトを経験した身として、今でも複雑な思いを抱くことがあります。 親は私の意思を尊重してくれましたが、その後の人生で経済的な自立が遅れた劣等感や孤独を思うと、本当はもっと、将来を一緒に見据えて応援してくれる伴走者でいてほしかった、と感じることもあるのです。
甘えではないか、と自分を責める葛藤そのものが、社会が定める自立という壁の前で立ち尽くす見えない孤独なのだと思います。だからこそ、今お子さんの傍で悩み、伴走し続けているあなたの粘り強い愛情は、もっと誇られていいはずです。
見守るあなた自身の心のために
お子さんを見守り続けることは、戦うことと同じくらい、あるいはそれ以上にエネルギーを消耗する作業です。
家族だからといって、一人で全てを背負う必要はありません。大人の発達障害と向き合うご家族に向けて、どのように距離を保ち、自分自身の生活を守っていくかという具体的なヒントを、専門のサイトが紹介しています。
大人の発達障害ナビ(ご家族・周囲の方々へ)

見えない孤独の中にいるのは、あなた一人ではありません。 いつか訪れる本当のゴールの時まで、まずはあなた自身を大切にしてください。
見守るという孤独な伴走の先に、時として「理解はできるが、肯定はできない」という、より険しい境界線に直面することがあります。その境界線をどう引き、自分と相手をどう守るのか。一つの答えとして、こちらの記事も併せてお読みください。