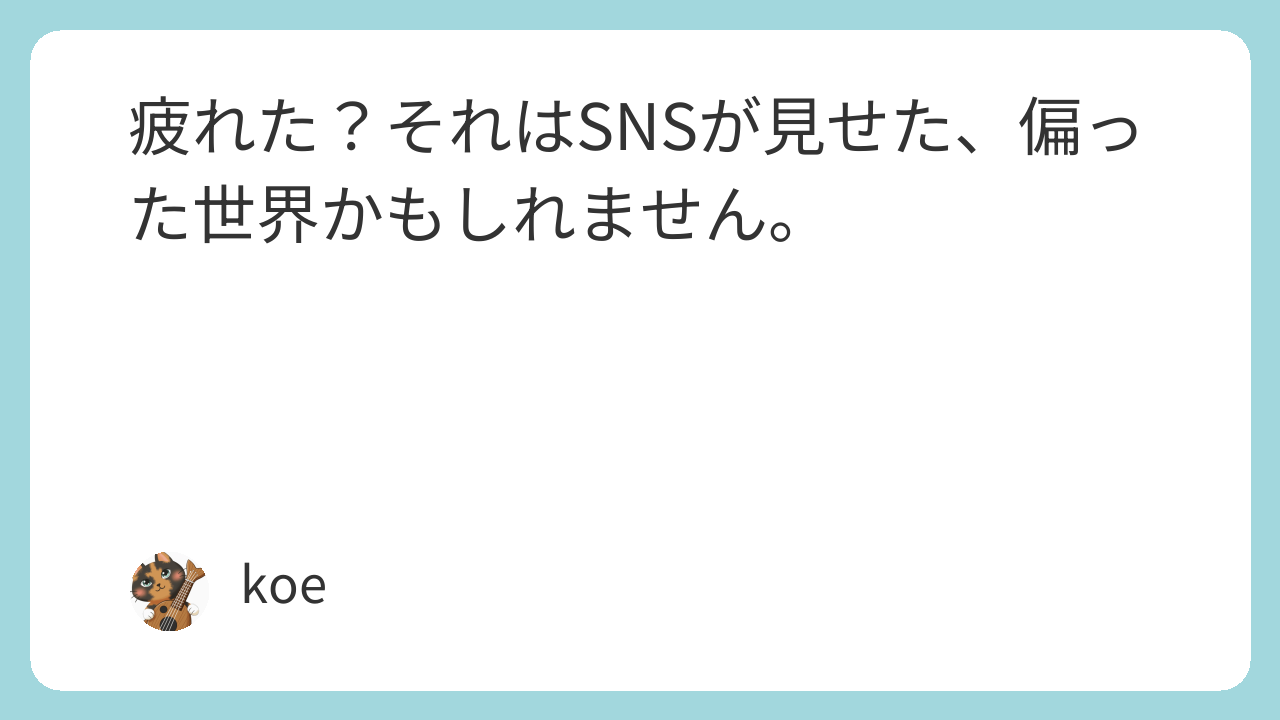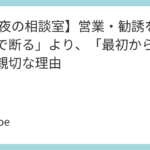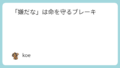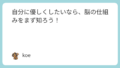SNSの居心地の悪さの正体
SNSを見ていると感じる、あの居心地の悪さ。
例えば、誰かの大変な投稿を見たとき、心の奥で「それに比べてうちは楽なのかも」「こんなことで悩んでいる自分は甘いのかも」と感じたり、
その逆で、「そんなことで騒いで、うちはもっと大変だ」「そんなの普通でしょ」という気持ちがわいてきたり。
そうするうちに「結局誰も私のことをわかってくれない」「私はこの界隈に属していない」「ここに居場所はない」「自分のことは自分でどうにかするしかない」という孤独感を募らせました。
SNSは、人との温かい交流やつながりと生み出す一方で、なぜこのような負の感情を抱くことになってしまうのでしょうか。
それは、ユーザーと親和性の高いコンテンツを優先的に表示するというアルゴリズムの仕組みによって、「あなたはこういう属性ですよね」と、勝手にラベリングされ、望んでいない情報を一方的に見せ続けられることへの疲れだと、私は考えていました。
実際、総務省の調査では、SNSで表示される情報がパーソナライズされていることを知っている人は約4割というデータが出てます。多いとも少ないとも言えない数かもしれませんが、私たちは、自分の意志とは関係なく、アルゴリズムに選別されていることを認識しつつあります。
アルゴリズムの罠と「エコーチェンバー」
この息苦しさの原因は、アルゴリズムによる表面的な疲れだけではありませんでした。
私たちが目にしているSNSの世界は、自分の意見や共感する情報だけが繰り返し返ってくる「エコーチェンバー(反響室)」という名の仕組みによって作られています。
自分の聞きたい声だけが反響し、それこそが世界のすべてだという錯覚を生む。この仕組みがまず、無意識のうちに私たちに「私はこの情報を受け取るべき人間だ」というプレッシャーを生み出します。
さらに、「声が大きい意見」ばかりが目につくことで、いつの間にか私たちの心の基準がゆがめられていきます。その基準と、自分の現実を比較したとき、私たちは「問題は私の側にある」「私が至らないからだ」と自分自身を矮小化し、孤独を深めてしまうのです。
「声が大きい」のは、ごく一部の少数派
オンラインコミュニティには、「90-9-1の法則」というものがあります。これは、ユーザーのうち90%が閲覧するだけ、1%がコンテンツを作成し、9%が時々反応するだけという構造を示す法則です。(Gigazine 「オンラインコミュニティの90・9・1の法則」より)
私たちは、タイムラインで目立つ「声の大きな意見」や、たくさんの「いいね」やコメントがついた投稿を見て、それが多数派の意見だと錯覚しがちです。
しかし、この錯覚を明確に否定する、衝撃的な事実があります。
調査を冷静に見てみましょう。
- 「自分の情報や作品の発表のため」にSNSを利用する人は、調査ではわずか12.0%にすぎません。この数字は、まさに法則でいうところの「1%(発信)+9%(反応)=10%の層」とほぼ一致します。(総務省「令和6年通信利用動向調査の結果」より)
- 投稿を見た人の中で実際にアクションを起こす人の割合(エンゲージメント率)は、ほとんどのSNSで数パーセント以下です。このエンゲージメントとは、「いいね」「コメント」「シェア」といった反応のことであり、SNS運用において最も重視される指標です。(NTTコム オンラインより)
これは何を意味するでしょうか?
あなたが日々目にしていた「活発な世界」は、実は残りの人々(約88%)という「閲覧専門の圧倒的多数派」の上に、わずか12.0%の人が起こした行動によって作り上げられた、極端に誇張された世界だったと言えます。
離脱者が作る、見えない偏り
さらに、この「声が大きい少数派」が支配する世界を見て、あなたと同じように、静かに離脱していく人がいることは想像に難くないはずです。
- 声の大きな情報に疲弊し、居心地の悪さを感じる人。
- 自分の静かな頑張りが、声の大きな困難と比べて「甘え」のように思えてしまい、どこにも混ざれない孤独感を感じる人。
疲れた人、静かに頑張る人が次々とその場を去っていくと、残るのは「声を上げ続ける人」の声ばかり。SNSは、「声を上げない静かな人がマジョリティである」という現実を覆い隠し、ますます極端に偏った世界を映し出しているのではないでしょうか。
世界は、あなたが思っているよりも広い
あなたがSNSで見ていたあの偏った世界は、決して現実のすべてを正しく表してはいません。
あなたがもし、あの世界を見て「自分の頑張りが足りない」「こんなことで悩むのは甘えだ」と自分を責めたり、孤独を感じているとしたら、それは違います。
あなたの心は、あの少数派の声が作り上げたノイズに騙されているだけです。
それは、客観的なデータが示しています。
実際には、「いいね」もコメントもしない、静かに見ているだけの人が多数派です。あなたと同じように、声を上げないけれど、静かに日々を乗り越えている人は、たくさん存在します。
あなたの悩みは、誰とも比較しなくていい、あなただけの正直な声です。SNSのノイズから離れて、この静かな場所で、ご自分の声に耳を傾けてみませんか。
参考文献・データ出典について
本記事で引用した「SNS利用者のアクション傾向」に関するデータや、SNSの構造に関する分析は、読者の皆さまに安心して読んでいただくため、以下の公開情報に基づいています。
- 総務省「令和6年通信利用動向調査の結果」 【発信者・多数派の根拠】 「自分の情報や作品の発表のため」にSNSを利用する人の割合(12.0%)など、日本のSNS利用行動に関する最新の公的データ。 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/data/250530_1.pdf
- 総務省「令和6年 情報通信白書」 【エコーチェンバーの根拠】 SNSで情報がパーソナライズされていることへの認識に関する公的データ。(グラフ33から45を参照)
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/datashu.html#f00342 - Gigazine 「オンラインコミュニティの90・9・1の法則」 オンラインコミュニティにおけるユーザー行動の偏りを示す法則についての解説記事。 https://gigazine.net/news/20241116-online-community-90-9-1-rule/
- NTTコム オンライン SNSにおけるエンゲージメント率の定義と重要性に関する解説コラム。 https://www.nttcoms.com/service/social/column/sns-engagement/