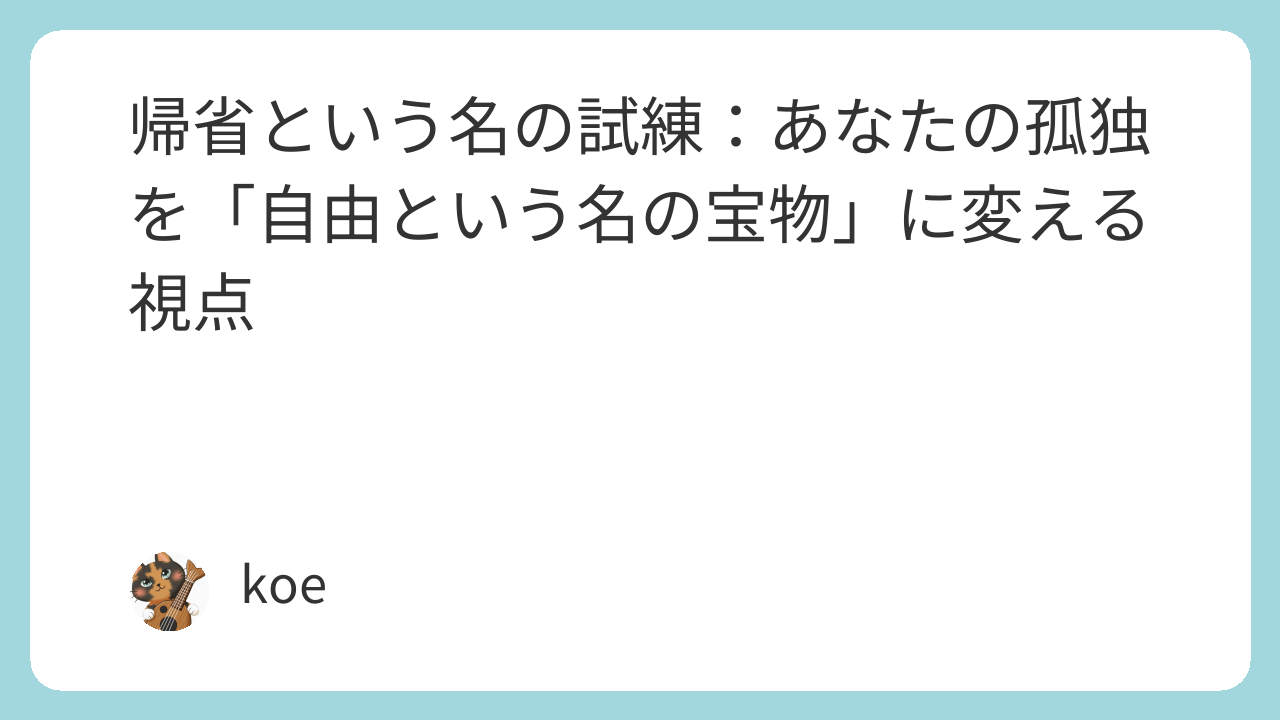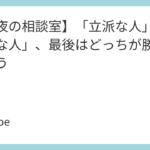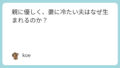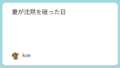※便宜上、夫や息子という表現をしていますが、妻や娘と置き換えても成り立つと思いますので、個々のパターンに当てはめて読んでいただければ幸いです。
前回のお話:「大切にされていない」という感覚について
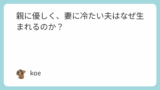
- 「無償の愛」と「等価交換の愛」の混同
- 「役割」と「個人」の混同
- 「承認欲求の循環」
この3つの原因によって、パートナーから「大切にされていない」と感じる状況が生み出されると述べました。
さて、この「大切にされていない」という感覚が、最も顕在化しやすい場所がどこか。
それは、年末年始やお盆の「帰省」です。これは、語り尽くされた、いわば風物詩ともいうべきイベントかもしれませんが、このココロノコエでも触れておきたいことです。
なぜなら特に、夫の実家への帰省は、夫が「息子」という役割に立ち戻ることで、妻が「夫の家族」の中に単独で放り込まれる孤独な状況を生み出すという、対等なはずの人間関係の中で、極めて特異な状況だからです。
夫は悪気なく「息子」に転生する
実家という特別な空間に足を踏み入れた途端、まるで魔法にかかったかのように、それまで家庭で頼もしい「夫」であったはずの存在が、何の悪気もなく「息子」へと転生してしまいます。彼らは、親の呼びかけに素直に応じ、子どもの頃のように甘え、昔の友人の話で盛り上がり、実家の居心地の良いソファでくつろぎます。
その姿は、決して悪いものではありません。
しかし、その「息子」としての振る舞いが、妻にとっての「夫」の役割を一時的に放棄することを意味しているのです。
「ちょっとこれ運んでくれるか」「お母さん、あれどこだっけ」といった、親との何気ないやりとり。それは彼らにとって、ごく自然な親子の交流です。
しかし、その間、妻は彼らの視界から完全に抜け落ちます。そして、妻は夫の親や親戚とどう話せばいいのか、何を手伝えばいいのか、何を期待されているのか、手探りで状況を読み取ることを強いられます。夫は、自分が「息子」として自然に振る舞っている間に、妻が「アウェイ」という孤独な戦場で孤軍奮闘していることに、まるで気づかないのです。
「大切にされていない」という無言のメッセージ
妻が抱える孤独感は、夫の行動によってさらに増幅されます。
例えば、夫が昔話に夢中になり、妻の存在を忘れ、会話の輪に入れてくれない時。あるいは、夫が自分の部屋にこもり、一人でゲームを始め、妻が義理の両親と何を話せばいいか困っていることに気づかない時。
これらは、言葉で「大切にしていない」と伝えているわけではありません。しかし、その無関心な行動こそが、妻に「あなたは今、私というチームメイトではなく、家族と過ごすことを選んだのだな」という無言のメッセージを突きつけるのです。
夫が家族と楽しそうに過ごす姿を見るたび、妻の心には「自分はここにいるべき人間ではないのかもしれない」という疎外感が芽生えます。
普段、二人で築いてきた夫婦というチームは、夫の実家という特殊な環境では、もろくも崩れ去ります。妻は、まるで夫の持ち物として実家に連れてこられたかのような感覚に陥り、自らの存在意義が揺らいでいるように感じてしまうのです。
妻の孤独を可視化する「タスク」と「感情労働」
この孤独は、単なる心理的な問題に留まりません。
多くの妻は、帰省中に見えない「タスク」と「感情労働」を背負わされます。例えば、食事の準備や後片付け。夫は「息子」としてくつろいでいる間に、妻は「お客様」として気をつかいながらも、台所に入り込み、手伝いを申し出なければなりません。それが自然にできなければ「気の利かない嫁」と思われかねない、というプレッシャーが常につきまといます。
さらに、義理の家族との会話は、高度な「感情労働」です。相手の気分を害さないように、適切な相槌を打ち、話題を見つけ、笑顔でいること。これは、普段から親密な関係を築けていない相手に対して行うため、心身ともに非常に消耗します。しかし、夫はこうした妻の苦労に気づくことはなく、ただ「楽しかったね」と帰路につくのです。
帰省後の「反動」と、再び築く夫婦関係
この帰省を経て、妻の心には深い疲労感と、ある種の不信感が残ります。それは、「もしもの時、この人は私を置き去りにするのではないか」という漠然とした不安です。この不安は、夫婦の関係を少しずつ蝕んでいきます。
しかし、厳しい現実を直視しましょう。夫にそこまでの「共感」や「繊細な努力」を期待することは、無駄な消耗を招く結果になりかねません。
敢えて言います。
あなたの孤独に気づけない、寄り添う努力を放棄したパートナーの態度は、結婚のチームメイトとしては、配慮に欠ける極めて未熟なものです。あなたがそれに深く傷つくのは、人間の心として当然の、そして最も健全な正当な反応です。
孤独は「自由」という名の宝物
私たちは、帰省先で「孤独」を感じた時、つい「私が気の利かない嫁だから」「私に魅力がないから」と自分を責めがちです。しかし、そうではありません。
あなたが孤独を感じたのは、あなたが優しすぎて、夫の役割を肩代わりし、彼に「夫」としての成長の機会を与えなかったからかもしれません。そして、あなたの孤独は、あなたが背負わされた「感情労働の対価」です。
夫が、あなたをチームメイトとして扱わないのなら、もう彼に期待するのをやめましょう。
夫婦というチームを築き直す努力が報われないのなら、あなたは「ソロチーム」として生きる自由があります。「帰省イベント」を共同で遂行する必要も、ないかもしれません。
あなたの孤独感は、「あなたは一人で何もできない弱い人間だ」という罰ではありません。それは、「あなたの時間と感情は、誰にも支配されない、あなただけの宝物だ」という、人生からの静かなメッセージだと、自分の中で書き換えてしまいましょう。
今日から、その孤独を恐れず、自分自身を大切にする時間に変えてみませんか。
あなたは、一人で孤独に耐える強い人ではありません。孤独を、自分を癒やすための時間に使える、勇敢な人になれるのです。