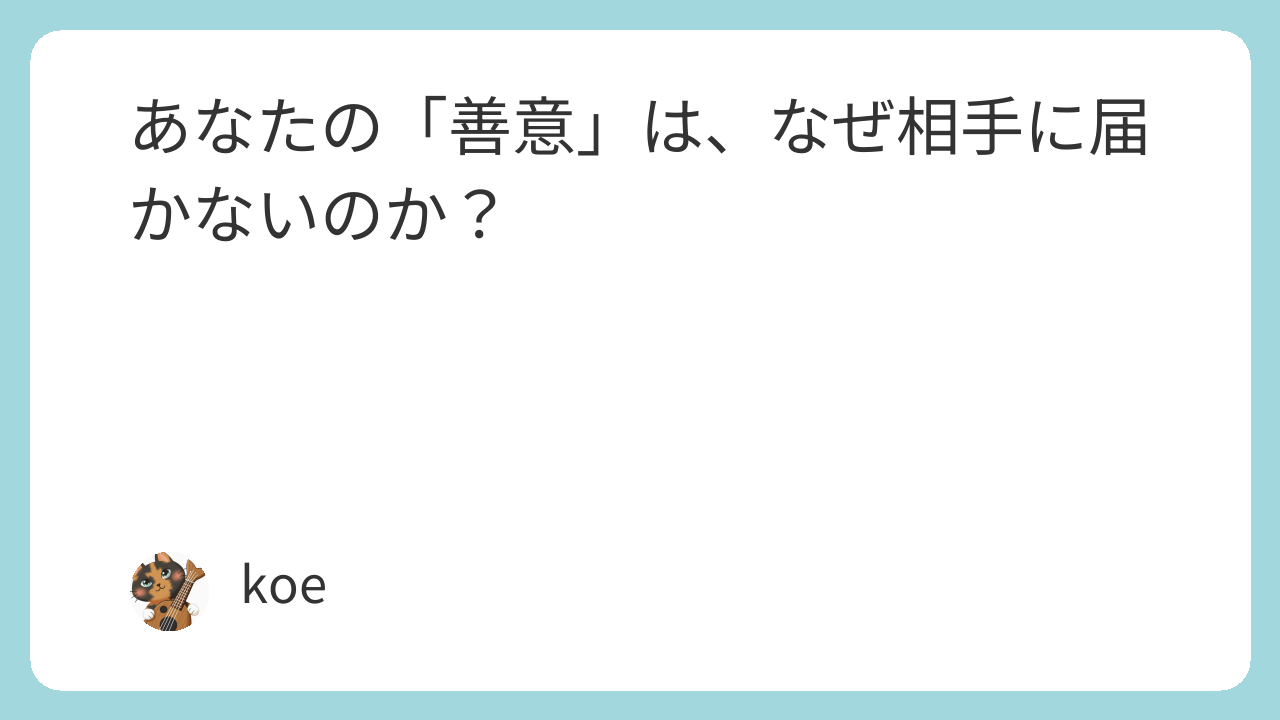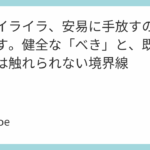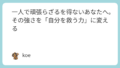「〜のつもり」という表現の二面性
「〜のつもり」という言葉は、人間関係においてしばしば摩擦を生む二面性を孕んでいます。
それは、「行為者の意図」と「受け手の認識」との間に生じる、埋めがたいズレを象徴しているからです。
まず、行為者にとっての「〜のつもり」は、自己弁護や意図の表明として機能します。「やってあげたかった」「手伝うつもりだった」といった言葉は、「私は悪意を持っていなかった」という無実の証明であり、「やろうという善意があったのだ」という自己肯定感の維持でもあります。
この心理の根底には、結果がどうであれ、自分の動機や努力を相手に理解してほしいという切実な願いがあります。
しかし、受け手にとっての「〜のつもり」は、往々にして不満や怒りの種となります。
「〜のつもりだったんでしょ?でも、何も伝わってこないし、結果も出てないじゃないか」という言葉の裏には、「意図だけでは意味がない」「言葉や行動で示してくれなければ、それは自己満足に過ぎない」という強いメッセージが込められています。
特に、期待を裏切られたと感じた時や、具体的な被害を被った時には、「やっているつもり」という曖昧な姿勢が、責任逃れや無責任さの表れだと受け取られ、不信感を募らせる原因になります。
このように、行為者と受け手の間には、「意図」と「結果」という、まったく異なる評価軸が存在します。
行為者は「意図」の純粋さを主張し、受け手は「結果」の不足を責める。
このズレは、両者の間に深い溝を作り、感情的な対立を生み出すのです。
建設的な対話への小さな一歩:紛争を乗り越えるスモールステップ
感情的な対立が激化し、言葉の応酬がエスカレートしてしまうと、互いの主張は平行線をたどり、解決の糸口は遠ざかります。このような時、どうすれば冷静さを取り戻し、再び建設的な対話へと舵を切ることができるのでしょうか。鍵となるのは、「本当に小さな、気づきレベルのスモールステップ」です。
1. 物理的な「間」を取る
言い争いが始まってしまったら、まず物理的に距離を取ることを試みてください。
これは、相手から逃げるのではなく、自分自身の感情を落ち着かせるための、最初の、そして最も重要なステップです。「ちょっと水を飲んでくるね」や「一度、トイレに行ってくる」など、些細な口実でその場を離れてみましょう。
ほんの数分でも、物理的な空間を分けることで、感情の熱量を下げることができます。この「間」は、無意識のうちにエスカレートしていた感情のループを断ち切る役割を果たします。
2. 相手ではなく、「自分の感情」に目を向ける
一人になったら、相手の非を数え上げるのではなく、今、自分がどう感じているかに意識を集中します。「なぜ自分はこんなに怒っているのだろう?」「この怒りの根源は何だろう?」と自問自答してみるのです。
もしかしたら、相手の言葉そのものよりも、過去の似たような経験や、自分の無力感、期待外れだったという失望感などが、怒りの本当の引き金になっているかもしれません。この内省は、相手を責めるエネルギーを、自己理解へと転換させるための、小さな方向転換です。
3. 「自分はなぜそうしたのか」を再確認する
冷静になったら、自分の「〜のつもり」という意図を、改めて客観的に見つめ直します。本当に相手のためだったのか、それとも無意識のうちに自分の都合を優先していなかったか。
この自己検証は、自分の「善意」が、実は傲慢さや配慮の欠如からくるものではなかったかを問い直す機会となります。このプロセスを経ることで、相手の立場への想像力が芽生え、単なる自己弁護から一歩踏み出すことができます。
4. 相手の言葉を「そのまま」受け止める練習
再び対話の場に戻る時、「相手の言葉をそのまま聞く」という意識を強く持ちます。相手が「あなたの〜のつもりという言葉で、私は傷ついた」と言ったとします。
この時、「いや、そんなつもりはなかった」と即座に反論するのではなく、まずは「そうか、傷つけたのか」と事実として受け止めてみましょう。この「受け止める」という行為は、相手の感情を尊重し、「あなたの気持ちはちゃんと伝わったよ」というメッセージを伝えることになります。
これは、非を認めることではなく、相手の感情を「知る」という、対話のスタート地点に立つための極めて重要なステップです。
5. 「意図」と「結果」を区別する
対話を再開する際に、まず「意図」と「結果」を明確に区別します。「私は〜というつもりでやったけれど、結果的にあなたを傷つけてしまった。それは申し訳ない」と伝えるのです。
これは、自分の「意図」を表明しつつも、相手が感じた「結果」に対する責任を認める、という二段階の構成になっています。
この伝え方は、相手の感情を否定することなく、自分の立場も説明できるため、互いの理解を深める土壌を築きます。
6. 「どうすればよかったか」を問いかける
そして最後に、相手に対して「どうすればよかっただろうか?」と尋ねてみてください。
これは、問題解決を相手に丸投げすることではありません。対話を通じて、今後のより良い関係を一緒に築いていきたいという意思表示です。
「〜のつもり」という過去の意図の是非を問うのではなく、「未来の行動」に焦点を当てることで、対立から協力へと視点を変えることができます。
これらのステップは、どれも一見、簡単そうに見えますが、感情が渦巻く中では非常に難しいものです。
しかし、もし一つでも実行できたなら、それは大きな進歩です。この小さな気づきの積み重ねが、やがて関係を修復し、より深い相互理解へと導く道筋となるでしょう。
なぜなら、人間関係の改善とは、大きな一歩を突然踏み出すことではなく、小さな一歩を何度も繰り返すことによって、少しずつ築かれていくものだからです。
さらに視点を広げてみたい方へ
人間関係の「意図と結果のズレ」は、ときに根深い問題へと繋がります。今のあなたの心境に合わせて、以下の記事も参考にしてみてください。
-
「相手に悪気はないと言い聞かせて、苦しくなっている」なら →
【正論じゃない】あなたが傷ついた事実に寄り添う、たった一つの大切な考え方 -
「謝ったはずなのに、何度も過去の話を蒸し返されて困っている」なら →
謝罪しても、許されない理由 -
「悪いと分かっていても、どうしても謝れなくて自己嫌悪している」なら →
「謝りたくない」は心が発するSOS。謝罪の強要がもたらす副作用
ひとつひとつの視点を繋ぎ合わせることで、あなたと誰かの間にある「信頼のタンク」を少しずつ満たしていけるかもしれません。