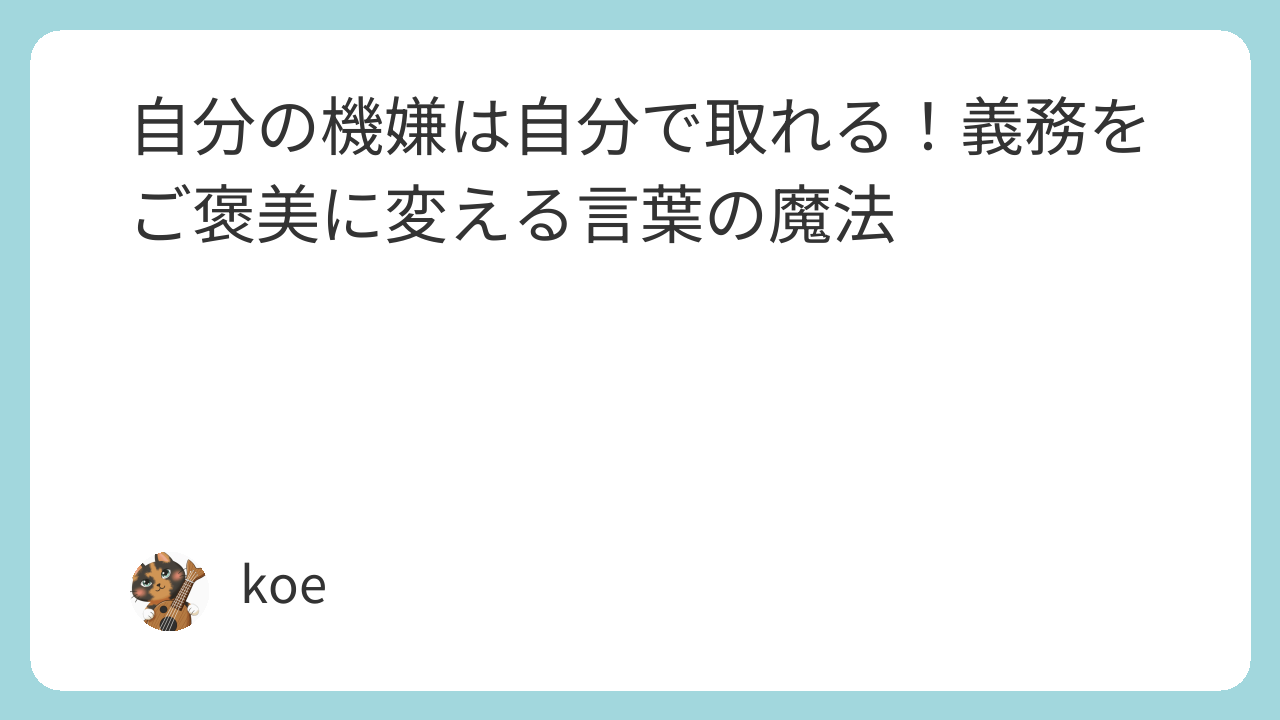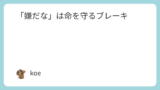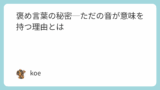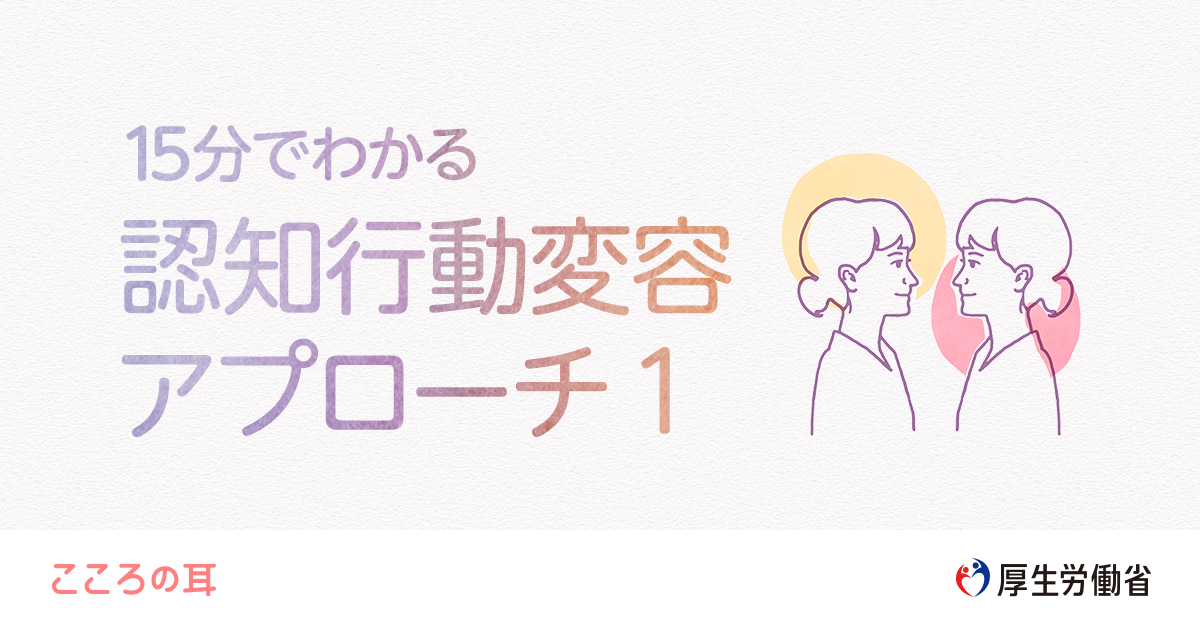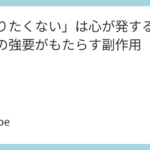職場で聞こえた、ある独り言
仕事終わりのロッカールーム。
さあ、今日はどんなご馳走食べようかな〜
誰に話しかけるでもなく、そう言いながら現れた先輩。その明るく前向きな雰囲気に、私はハッとしました。
なぜなら、その瞬間の私の心の中は、正反対だったからです。
仕事が終わった解放感はあるものの、あー、今日の晩ご飯どうしようと、次に控えるタスクへの面倒くさいという思いで、思考が重くなっていたのです。
先輩の言うご馳走が、本当に豪華な料理かどうかは分かりません。でも、いつもの家事をあえてご馳走と表現することで、自分の中でポジティブに変換している。これは、まさに言葉の力技だ!と衝撃を受けたのです。
人生という車を動かすアクセル
以前、別の記事(嫌だなは命を守るブレーキ)で、私たちの心には止まるためのブレーキ(不快な予知)が必要だと書きました。でも、車を安全に走らせるためには、同時に前へ進むためのアクセルも欠かせません。
先輩のご馳走という独り言は、まさにこのアクセルを軽やかに踏み込むための心の技術でした。
面倒くさいという嫌な感情が湧き上がる前に、自分にとって価値のあるご馳走という言葉をぶつける。そうすることで、脳の中のブレーキを報酬の予感で塗り替えていたのですね。
この言葉が自分への報酬に変わる仕組みについては、関連記事(褒め言葉の秘密)で詳しく解説していますが、先輩はこの理論を、誰に教わるでもなく日常の中で実践されていたのです。
今日からできる心の準備運動
理屈はわかっても、いきなり先輩のようにポジティブな言葉を出すのは難しいかもしれません。でも、これは才能ではなく、意識して鍛えられる心の筋力トレーニングです。
まずは、一日の中の小さな心地よい瞬間を、言葉でマーキングすることから始めてみましょう。
・ひとくち食べて、美味しい!
・お風呂に浸かって、幸せ〜
・掃除をして、スッキリした!
ポイントは、感情が溢れるのを待つのではなく、その瞬間を言葉で捉えに行くことです。その習慣が積み重なると、あなたの言葉は、あなた自身の脳を動かす魔法の合図に育っていきます。
あなたの言葉で、日常の義務をご褒美に変えていく。
その積み重ねが、自分を一番の味方にしてくれるはずです。
もっと深く知りたい方へ
⑴今回のアクセルの役割とセットで読んでほしいのが、自分を守るためのブレーキの話です。
関連記事:嫌だなは命を守るブレーキ
⑵また、今回ご紹介した「言葉がご褒美に変わる仕組み」の詳しい理屈については、こちらの記事で解説しています。
関連記事:褒め言葉の秘密─ただの音が意味を持つ理由とは
⑶さらに、「考え方や行動を整えて、心を楽にする方法(認知行動変容アプローチ)」について、より詳しく学べる公的な学習ツールがあります。職場のメンタルヘルス対策の一環として公開されているものですが、日常生活にも活かせるヒントが詰まっています。
こころの耳:15分でわかる認知行動変容アプローチ
まずは、自分自身の心のポジティブな一瞬を切り取る練習から始めてみませんか。