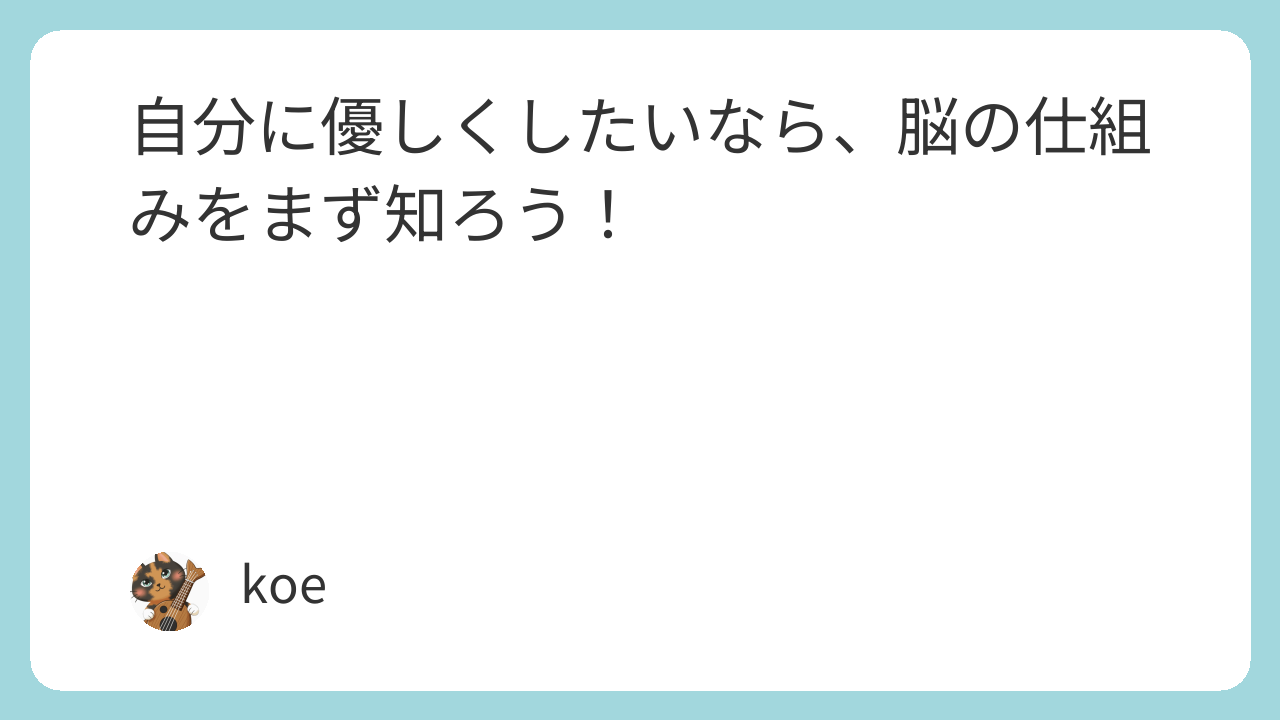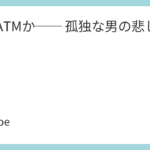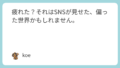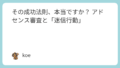先日ふと、素朴な疑問が浮かびました。
誰よりも常に私たちのそばにいて見守っている存在、それは私たち自身そのものなのに、自分で自分に優しくなれないのはなぜなのだろう?
うまくいかなかった時、
「自分が至らなかったからだ。」
「もっとああしていれば良かった。」
「もっと頑張れたはずだ」と、自分を責めたり、過去の自分を恨んだりもする。
もちろん、もっとより良い自分になりたいという克己心が強いから良いことだ、とも言えるでしょう。しかし、それが過剰になると、自分を傷つけ疲弊する原因にもなってしまいます。
なぜそんな意地悪を、自分に対してしてしまうのでしょうか。
この記事では、脳科学の視点から、その仕組みを紐解いていきます。
古い脳、新しい脳
私たちの脳には、大きく分けて2つの働きがあると言われています。
一つは、感情や直感、生存本能を司る「古い脳」。
もう一つは、論理や理性、計画性を司る「新しい脳」です。
ここでは、古い脳を「あなたを危険から守ろうと必死なベテラン兵士」、新しい脳を「状況を冷静に判断しようとする司令官」とイメージしてみてください。

問題は、危険を察知した時、兵士の反応が司令官の判断よりも、圧倒的に速く、そして強いことです。
生存を司る古い脳においては、個の利益より集団の利益が優先される
人間は、集団で協力することで生き延びてきた歴史があります。
そのため、私たちの古い脳には、集団から孤立することを「死」に直結する最大の脅威として認識するプログラムが備わっています。
玉川大学の鮫島和行准教授の解説にも、このような記述があります。(※1)
不確実性やリスクを避け、他者と協力するような行動が「デフォルト(初期設定)」として備わり、素早い意思決定をする際にはデフォルトが発動されて非合理的な行動が出てしまう、という説明である。
つまり、私たちの脳は、生まれつき「他者と協力すること」を最優先するように設定されている、ということです。
この「初期設定」があるために、自分が何か失敗をすると、それは単なる個人の問題ではなく、「集団に迷惑をかける」「自分の評価が下がり、集団にいられなくなる」という、生存を脅かす危険信号として認識されてしまいます。
失敗した時に起きること
では、失敗した時、脳の中では何が起きているのでしょうか。
それは、「古い脳の反応」と「新しい脳の対応」の二段階に分けられます。
古い脳の反応(万人に共通)
まず、失敗によって「集団から排除されるかもしれない!」という生存の危機を、古い脳が本能的に察知します。
これは理屈ではなく、「怖い」「まずい」という強烈な感情的なパニックです。
この警報は、文化や育ちに関係なく、人間であれば誰もが持つ普遍的な反応です。
新しい脳の対応(文化などの育ちによって変わる)
次に、この古い脳が鳴らした警報を、新しい脳が受け取ります。
新しい脳は、このパニックを鎮めるために、「どうすればこの最悪の事態を避けられるか?」と解決策を探します。
この時、自分が属する社会で学習してきた「文化」や「成功体験」という名の対応マニュアルを参照すると考えられます。
日本人の傾向
日本人は成功も失敗も努力に関連付ける傾向が強いため、失敗しても成功しても自分を責めがちです。また、失敗をしたときには、自己批判的な態度が周囲の批判を抑えることもあることも指摘されています。(※2)
つまり日本の文化では、原因究明や再発防止策よりも先に、この「反省の態度」がないと、誠意がないと見なされ、集団からの信頼を回復するのが難しくなることがあるのです。
ここからは筆者の考察になりますが、この文化的な背景と、先ほど述べた古い脳が発する「警報」を合わせて考えると、興味深い仮説が浮かび上がります。
それは、古い脳が発した「集団から孤立したくない」という強い恐怖信号に突き動かされる形で、私たちの新しい脳が、社会的な解決策として「反省の態度=自己批判」という行動を戦略的に選択しているのではないか、という可能性です。
自分に厳しくしてしまうのは、こうした脳の仕組みと文化的な学習が、複雑に影響し合った結果なのかもしれません。
自分に優しくするのは新しい脳の働き
ここまで見てきたように、自己批判は、古い脳が鳴らした警報に対して、新しい脳が慌てて対応している「パニック対応」のようなものです。
しかし一方で、新しい脳は「自分に優しくする」という、より高度で成熟した働きかけもできるのです。
そもそも、私たちの脳は、感情を司る古い脳が先に発達し、理性を司る新しい脳(特に前頭前野)はゆっくりと成長して、20歳代にようやく完成すると言われています。(※3)
つまり、「自分に優しくする」というのは、生まれ持った才能ではなく、新しい脳を育て、意識して練習していく「技術」なのです。
それは、パニックになっている兵士(古い脳)を、司令官(新しい脳)が「大丈夫だよ」となだめてあげるような、脳内のコミュニケーションスキルと言えるでしょう。
司令官として、できること
では、具体的にどうすれば、司令官は兵士をなだめることができるのでしょうか。
まず大切なのは、自分を責めている時、「ああ今、兵士が私を守ろうと、必死に警報を鳴らしてくれているんだな」と気づいてあげることではないでしょうか。
その上で、司令官として、兵士にこう語りかけてみてください。
「危険を知らせてくれて、ありがとう」
「でも大丈夫。これは命に関わるような状況じゃない」
「ちゃんと私がいるから、一緒に考えよう」

すぐに自己批判が止まらなくても、問題ありません。
この脳の仕組みを知り、自分の中で起きていることを客観的に眺めてみる。
それだけで、私たちは自分を責める悪循環から、一歩抜け出すことができるはずです。
参考文献
(※1) 鮫島和行 (2016) 「人の行動を決める古い脳と新しい脳」 生協研究480号p.19-25
(※2) 一般社団法人 日本産業カウンセラー協会『働く人の心ラボ』(2023) どうして自分を批判するの? 心理学が教える自己批判の原因と悪影響
(※3) 東邦大学 ストレスと脳 | 生物学科