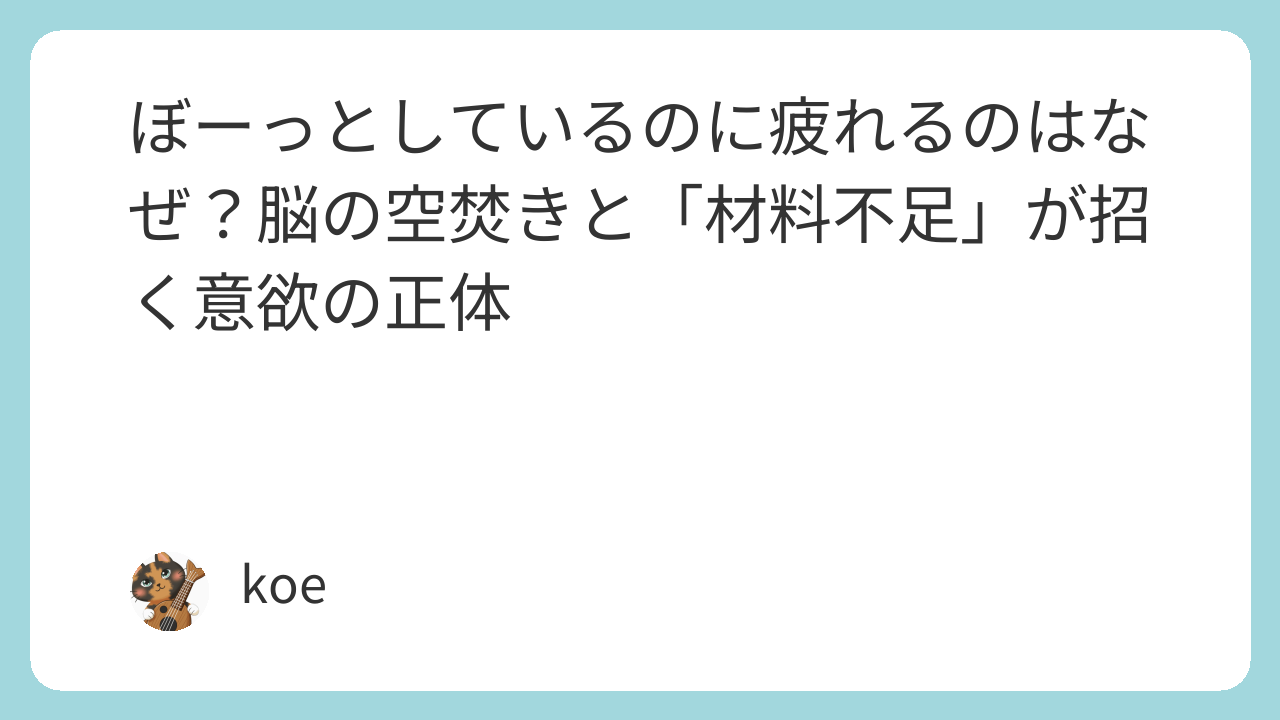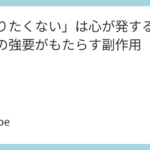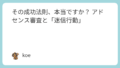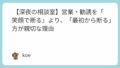はじめに。
この記事は、特定の症状を診断したり、治療法を推奨するものではありません。記載の内容は、筆者の個人的な経験と、公開されている一般的な情報に基づく考察です。明らかな心身の不調や、長期にわたる意欲低下がある方は、この記事を参考にせず、必ず医療機関(心療内科、精神科など)へご相談ください。
自力で回復可能な方を対象とした、一つの視点の提案です。
人間関係という労働のあとで
誰かの顔色を伺い、場を整え、言葉を選び抜く。 人間関係は、それだけで膨大なエネルギーを必要とするものです。
外で働くことだけでなく、家庭内という密室で行われるケアも、終わりも対価もない高度な感情の労働です。そんな一日を終えて、ソファに倒れ込みながらスマホをダラダラと眺めてしまうとき、私たちはどこかで自分を責めてはいないでしょうか。
もっと有意義な時間の使い方があったはずなのに。 私はなんて意志が弱いんだろう。 気づけばずっと画面を眺めていませんか。(私はそんな時がありました😂)
でも、その動けなさには、脳科学的にも物理的にも、切実な理由があったのです。
脳が勝手にエネルギーを浪費する仕組み
なぜ、休んでいるつもりなのに疲れが取れないのか。最近、その謎を解き明かしてくれる非常に示唆に富んだコラムに出会いました。脳科学の視点から現代人のメンタル不調を分析している、プレジデントオンラインの記事です。(※1)
引用: 不安やうつを抱える人の脳はDMNを中心にむしろ過剰に活動しており、「働きすぎて疲弊している状態」にあるのです。 (中略) 情報があふれる現代社会だからこそ、意識的にこのDMNの暴走を鎮め、脳を休ませてあげる必要があります。
(出典:ウォーキングよりも音楽よりも効果的…「6分でストレスを最大68%軽減する」ゴロゴロしながらできること #プレジデントオンライン
この記事を読んで、私は点と点がつながるような気がしました。
私たちの脳には、意識して何かに集中していない時にこそ活発に動き出すデフォルト・モード・ネットワーク(DMN)という回路があるんだそうです。もともとこのDMNは、脳が過去の経験を整理したり、創造的なアイデアを生み出したりするために欠かせない大切な機能です。
ところが、この回路が暴走すると、脳は過去の後悔や未来の不安をぐるぐると反芻(はんすう)し始めます。自分ではぼーっと休んでいるつもりでも、脳内ではずっとエネルギーが浪費され続けている。いわば、エンジンの空焚き状態だったのです。
物理的に削り取られる心の材料
この脳の空焚きは、単なる気分の問題ではありません。私が今学んでいるメンタルヘルス・マネジメント検定のテキストには、その物理的な消耗の仕組みが記されていました。(※2)
強いストレスが加わると、それに対抗しようと体内では抗ストレスホルモンを出すために、ビタミンB・C群などの栄養素が猛スピードで消費されていきます。さらに、ストレス下ではタンパク質の代謝も促進されます。
したがって、脳の過活動が起きているとき、私たちの身体の中では、大切な材料が物理的に奪い取られ、枯渇してしまっていたのです。
私たちは、ストレスへの対処として低コストに(スマホなどで)休んでいるつもりでも、体内では通常と変わらず、あるいはそれ以上に消耗を続けていたということ。ちょっと皮肉な仕組みですよね😅
復活の答え合わせ:私が身をもって知ったこと
実は私自身、かつて理由のわからない体調不良に悩まされ、動けなくなっていた時期がありました。当時は「なぜか分からないけどだるい、横になっていたい、ダラダラしていたい」という状態で、今振り返ると、まさにこの「脳の空焚き」と「材料不足」のループの中にいたのだと分かります。 何を食べて過ごしていたのかも思い出せません😅
さすがにこれはおかしいのではないか?と、いくつもの病院を訪ね、自分の身体の状態を一つずつ確認していく中で知った、鉄分などの微量元素の大切さ。身体を整え、他者との対話を通じて心が落ち着いていく感覚が、私を救ったのだと思います。 なぜなら当時、自分自身のメンテナンス、つまり自身のヘルスケアという視点は全く持っていなかったからです。
私にとって大きな転機となったのは、自分の状態を客観的に、理屈で捉えられるようになったことでした。
今感じているこの苦しさは、一体どういう仕組みで起きているのか。そうやって冷静に分析し、「いつか来る終わりの日を不安の中で過ごすよりも、今この瞬間をやりたいことをして気分良く過ごす方が大事だ」と、意識の矛先を切り替えられるようになったのです。
身体の材料を整え、考え方のクセを少しずつ変えていく。その結果、心に小さな余白が生まれました。その余白のおかげで、以前なら諦めていたような習い事を始めることができ、フィットネスやプロテインでの栄養補給も、自分を支える大切な習慣になりました。
「材料を補い、身体と捉え方の両面から整える」という順番を辿った結果、あんなに動けなかった私が、今では数年間の肉体労働をやり遂げ、接客の仕事にまで復帰しています。
「不安」という痛みへの生存戦略
理想に燃えた若い頃には、上手く出来ない自分、つい怠けてしまう自分を責めがちでした。しかし、自分を責めるのをやめたとき、そこに生まれたのは「不安」でした。
自分を責めている間は、まだ「自分のせいだ」という納得感でその場を凌げたのかもしれません。でも、「自分にはもう、この現状をどうにもできない」と、自分を責めることすら出来ない無力感から来る不安は、実に耐えがたいものです。
その不安から逃れるために、私たちはスマホの画面を眺めます。指先を動かし、次々と流れてくる情報を脳に流し込むことで、不安の声をかき消そうとする。
それは怠慢ではなく、剥き出しの不安から自分を守るための、切実な防衛反応なのだと思います。
だから、スマホを眺める自分をどうか許してあげてください。今はそうやって、やり過ごすことが最優先だから。
ただ、もし「いつまでこの不安の中にいなきゃいけないんだろう」と感じるなら、それは意志の力で解決しようとするのではなく、身体の「材料」を補うことから始めてみてはどうでしょうか。
脳の空焚きを鎮めるための栄養を摂り、身体の土台を少しずつ整えていく。材料が満たされ、脳の無駄な浪費が収まってくれば、「空白の時間」を満たすものが、少しずつ穏やかなものに変わっていきます。
そうなれば、不安を打ち消すためのスマホではなく、自分の「やりたい」のために時間を使える日が、きっと自然にやってくるはずですから。
※この記事は筆者の個人的な体験と学習に基づく記録であり、特定の治療や診断を目的としたものではありません。
参考サイト
※1
※2
大阪商工会議所
メンタルヘルス・マネジメント検定試験公式テキスト III種 セルフケアコース〔第5版〕